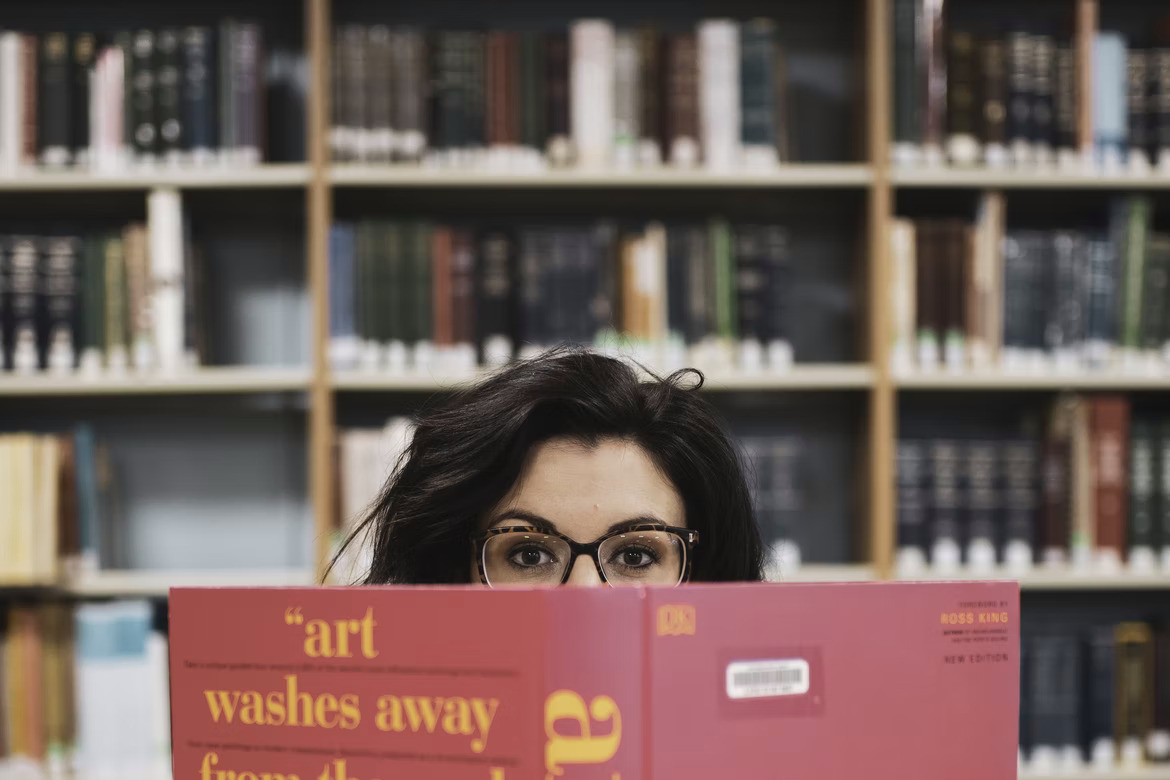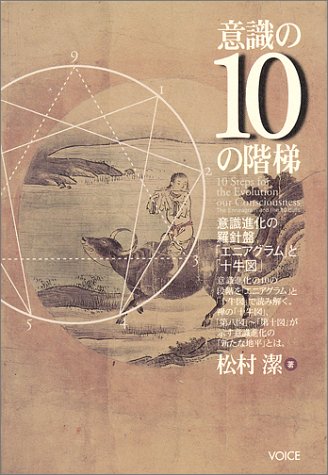記事の文字数が増えるにつれてブログが重くなり
なかなか更新できなかったりエラーが出ることが続いたため
後半記事を作ったのですが、それすらも追記困難になるほど
コンテンツが増えてきました。
そのため後半記事をさらにいくつかに分け、こちらのページでは
「参考図書」専用③<スピリチュアル>として新たに設定しました。
前半記事:前半記事その1、前半記事その2:セルフ・コントロール①、前半記事その2:セルフコントロール②
後半記事: その1<各改善法の詳細> 、その2<おすすめ情報源>
その3参考図書①<栄養療法>、その3参考図書②<精神医学・心理学>、その3参考図書③<スピリチュアル> 、その3参考図書④<その他>
目次
参考図書
記事の中で取り上げた(一部はそれ以外も)良書をリストアップしておきます。
その他
『脳を鍛えるには運動しかない!』
「メンタルを改善したければ、身体を刺激して強化せよ」。
ともすれば経験則や根性論のようにいわれがちですが、これが脳科学的に証明される研究成果が、2000年代に入ってからいくつも発表されています。
定期的にきつめの有酸素運動をすることで、記憶力・集中力・認知判断力が向上し、逆に不安やうつ状態が明らかに改善するのです。
またアメリカうつ病学会でも2010年のガイドラインからはうつ病に運動療法を治療法の1つとして正式に載せるなど、運動が注目されるようになってきました。
本書では運動によってうつや不安が減り、学業成績が上がり、ADHD(注意欠陥多動性障害)が改善し、更年期障害の改善さらには認知症予防の可能性まで、豊富な事例とともにそれぞれの病状に対する推奨運動法を教えてくれています。
『アドレナル・ファティーグ』
原因不明の慢性疲労、特に午前に強くて夕方以降に軽減するタイプなら「副腎疲労症候群」かもしれません。
しかしこれは正式な医学的病名ではありません。医学では、副腎皮質ホルモンが更に欠乏し、症状面でも検査値面でも明白になって初めて「アジソン病」と認定されます。
が、実際にはアジソン病までいかない時点のホルモン欠乏でも自覚的には様々な症状を感じ、そのせいで仕事や勉強はもちろん、日常生活ですらまともに送れなくなっている人もいるのです。
日本の著者による副腎疲労症候群の本も何冊か出ていますが、ここでは本書をお勧めします。具体的な改善法が詳しく述べられています。例えば以下のように。
①何年も心身の無理を重ねた後に発症しやすいこと、ネガティブ思考の人に置きやすいという部分を認め、精神面の改善が必要だと知ること。
②食生活をはじめとする生活習慣の改善を徹底して行なう必要があること。
『つらい不調が続いたら慢性上咽頭炎を治しなさい』
「慢性上咽頭炎」とは、鼻の奥に位置する「上咽頭」が慢性的に炎症を起こしている状態です。
特に鼻の違和感がないため、多くの人はこの疾患について自覚症状がありません。
しかしこの炎症が頭痛、慢性疲労、めまい、慢性の鼻水・鼻づまり、慢性の咳、胃腸の不調の原因になっており、この炎症を抑えることで不調が改善することが近年明らかになり、耳鼻科医や内科医の間で注目を集めつつあります。
本書はこの「慢性上咽頭炎」のメカニズムと、その治療法について説明しています。
『神田橋條治が教える 心身養生のための経絡・ツボ療法』
独自の深い精神科臨床法を長年にわたり開拓し、何冊ものロングセラー本を出版し、また近年では発達障害の人向けの漢方薬処方を開発して、それは通称「神田橋処方」として現場で活用されるようになっています(従来は漢方薬は向精神薬の副作用をある程度抑える作用くらいで、精神科領域では役立たない、とみなされていた中で、です)。
神田橋氏は人の心身のつながりや、病気とはエネルギー的な乱れや滞りからくるとの実感から、本書ではそれを読者が自ら実行できるさまざまなタッチングセラピー的手法を伝授しています。
本書は紙版もありますが、電子版がお勧めです。なぜなら本文中にある、施術実施動画(You Tube )に、文中のリンクから即座に飛べるという便利さがあるからです。もちろん紙版でもURL をパソコン等に入力すれば飛べますが。
『ネイチャーフィックス』
副題に「自然が最高の脳をつくる 最新科学でわかった創造性と幸福感の高め方」とあるとおりの内容です。
どんな心身の不調時にも、無自覚のうちに確実に気分も体調も良くなる。
1ヶ月に5時間以上、自然の中(都心の公園でもOK )で過ごすだけてうつや不安その他の不調が癒やされます。
その効果は瞑想以上です。
また、観葉植物が視界にあるだけでも落ち着きや集中力が上がるので、ADHDをはじめとする発達障害やHSP(過敏タイプの人)にも非常に有効です。
メディカルアロマセラピー
・『医師がすすめるアロマセラピー決定版』
著者は痛みへの補助療法として自らのクリニックでアロマセラピーを取り入れ始め、1997年には日本アロマセラピー学会を立ち上げ、日本での医療分野におけるアロマセラピーを確立した医師です。
痛みやかゆみ、喘息症状の緩和などの事例とEO のレシピを掲載。
ヤングリビング社のEO(YL-EO)ではないので内服という手段は使えないですが、YL-EO以外の、一般販売されているEOで少しでも実用的に活用したい人には、参考になるでしょう。
カラーセラピー、絵画療法
・『心を探る色彩マップ』
著者の松村潔氏独自の絵画療法である「ライフシンボル」では「色」「位置」「数」を主要な要素として絵や図を解釈しています。
本書ではそのうちの「色」と「位置」の要素のみを取り上げた簡易版ですが、
ライフシンボルの入門書として読んでみると良いでしょう。
ライフシンボルについては
http://www.yulisroom.jp/archives/2005/07/post_73.html および
https://heart-art.jp/category/subconsious_art_factors
もご参照。
・『大アルカナで展開するタロットリーディング 実践編』
松村流絵画療法である「ライフシンボル」では絵や図をみたとき、
「色」「位置」「数」を主要な要素として解釈していきます。
タロットの大アルカナをその視点から解釈すると、従来とはひと味もふた味も違った見方ができ、また個々のバラバラな意味を単に暗記する必要がなく
論理的に考えれば良いことがわかってきます。
ちなみに絵画療法的には、自分が何気なく描いたタロットの大アルカナを
その視点から読み解くと(『心を探る色彩マップ』で基礎学習して)、
自分の内面が驚くほど露呈していることがわかり、笑ってしまうほどです。
・『意識の10の階梯―意識進化の羅針盤「エニアグラム」と「十牛図」』
「十牛図」とは意識が進化する際の流れを10段階に示した絵で、禅の修行時に使われたものだそうです。
著者はこれとエニアグラムを対応させ、独自の考察を行なっています。
松村流絵画療法である「ライフシンボル」では十牛図とタロットの大アルカナを素材に描くことが多かったのでここにも参考に挙げておきますが、
相当マニアックな内容なので、本当に興味のある人のみ、読むと良いでしょう。
ちなみに http://www.yulisroom.jp/archives/2005/07/post_75.html には、松村流十牛図の説明と、(蛇足ですが)2002年頃に描いた私なりの十牛図の例を残しています。
前半、後半記事群へのリスト
前半記事:前半記事その1、前半記事その2:セルフ・コントロール①、前半記事その2:セルフコントロール②
後半記事: その1<各改善法の詳細> 、その2<おすすめ情報源>
その3参考図書①<栄養療法>、その3参考図書②<精神医学・心理学>、その3参考図書③<スピリチュアル>、その3参考図書④<その他>